✅ 目的文(この記事で伝えたいこと)
この記事は、「ふるさと納税ポイント還元廃止」の裏側で何が起こっているのかを知りたい人に向けて書いています。
表向きは“制度の健全化”と言われているけれど、実際には誰が得をし、誰が損をしているのか。
なぜ国民だけが静かに「還元」を奪われているのか──
その構造と責任の所在を、具体的に掘り下げます。
🧩 冒頭文
「ふるさと納税のポイント、今年で終わるらしいで」
そんな話を聞いたのは、2024年の夏ごろやった。
最初は「まぁ、しゃあないか」「制度の見直しやろな」って、正直あんまり深く考えてへんかった。
でもやで──
調べれば調べるほど、「ん?」っていう違和感が積み重なってきたんよ。
「なんでポイントだけが禁止されるんや?」
「企業は? 官僚は? ほんで、僕ら国民は?」
この制度、静かに“かたち”が変わっただけやない。
静かに“得する人と、損する人”が入れ替わってたんや。
僕はふるさと納税そのものを否定したいわけちゃう。
でもな、「ええ制度」が“運用でねじまげられて”、
誰も責任取らんまま、「改革したフリ」だけで通されるんやったら──
それは、さすがに黙っとられへんわ。
第1章|僕はふるさと納税という制度そのものは「良いもの」だと思っていた

ふるさと納税っていう仕組み自体、僕は今でも「ええ制度」やと思ってる。
都会に住んでても、自分が応援したい地方に税金をまわせる。 「どうせ取られる税金」やのうて、「ここに使ってほしい」って、ちょっとだけ選べる余地がある。 それって、納税者にとっても、自治体にとってもプラスになる仕組みやと思うねん。
返礼品もな、ただの“おまけ”やなくて、 「こんなん作ってる地域なんやなぁ」って興味持てるきっかけになるんよ。 美味しいもん届いたら、次はそこに旅行してみよかなって思うこともあるし。
ルールもしっかり決まってて、 返礼品は寄付額の3割まで、自己負担は2000円だけ。 上限額内でやれば、所得税や住民税から控除される。
つまりやな── 「納税を通して地方を応援できて、ほんで自分もちょっと得できる」 そんな、ええバランス取れた制度やってん。
僕も毎年、上限額ちゃんと調べて、家族と一緒に返礼品選んでた。 ほんまに、「ようできた仕組みやな」って思ってた。
──せやけど、「あの通達」が出るまではな。
もっと正直に言うと、どうせ無理やり税金取られるんやったら、少しでも取り返したろうって思っただけやねん。 国はいつも“取ること”ばっかり考えて、僕らにちゃんと返そうとはしてくれへん。いや返さんでもええから、もうあまり搾取しないでくれ。 それが「悪いこと」やって言われる筋合い、あるんか?
第2章|でも、2024年秋──制度は静かに“変質”した

2024年10月── 総務省から「ふるさと納税でのポイント還元は禁止」との通達が出た。
理由はこうや。 「過度な競争が、制度本来の趣旨に反する」
一見もっともらしい言い方やけど、正直言って──僕はよくわからんかった。
ポイントがあるからこそ、他の寄附よりも“選ばれる理由”があった。 それが急に「制度の趣旨に反する」って言われても、なんやろな…… 「あれ?なんか急に雰囲気変わったな」って、そんな感覚のほうが強かった。
たとえば楽天ふるさと納税みたいに、 ポイント還元をうまく使って寄附を集めてたサイトほど、今回の通達は“死活問題”になった。
ほんで実際、ポイント還元が禁止されたあとは──
- 国民:還元を受けられなくなった
- 楽天など:集客力がダウン
- 自治体:手数料はそのままで、寄附の競争力も落ちる
これ、誰のための「改革」やったんやろな?
しかも、還元だけをピンポイントで禁止して、 問題視されてた“高すぎる手数料”にはノータッチって。
その時点で、「あ、これ誰かが“得”する構造やな」って気づいたんよ。
この制度、そもそも“寄附”っていう建前の中に、 実はたくさんの利害が絡んでる。
表向きは「制度の健全化」やけど、 裏では静かに“金の流れ”が変わった──そんな感触やった。
第3章|ポイントが消えて、誰が得して、誰が損したのか

ポイントがなくなったことで、最も得をしたのは──実は“企業”やった。
ふるさと納税の仲介サイトを運営する企業は、これまでポイント還元の原資を一部負担してきた。
それが今回の「禁止」で不要になったんや。
その結果どうなるか?
→ ポイント分のコストが浮く。つまり、企業側の利益率がアップする。
逆に──
損をしたのは誰か?
✅ 国民:
今まで、実質的に“税金の還元”としてポイントがもらえてたのがゼロに。
返礼品+ポイントで考えてた人にとっては、「2000円の自己負担」の重みが増した。
✅ 自治体:
楽天などの仲介サイトに掲載してもらうために、寄附額の最大2割を手数料として支払っていた立場。
制度改正でポイント還元がなくなったことで、寄附が減少すれば、そのぶん自治体が自由に使えるお金も減る。
しかも、高い手数料はそのまま据え置き。
自分たちでルールを変えられる立場やないのに、結果的に“損”を背負わされた──
つまり、“被害者”は国民と自治体やったんや。
✅ 楽天などの集客型サイト:
ポイントを全面に出して寄附を集めてたサイトにとっては、明らかに不利。
還元ナシ=利用者の離脱。企業努力が否定される格好や。
──そう、これって要するに、
“ポイント戦”に強かったプレイヤーが潰されて、関係のない企業だけが得をした構図。
しかも、還元を楽しみにしてた僕ら国民にとっては、
「なんとなく損した気分」じゃなくて、実質的に“税金の還元が減った”という現実やった。
それでも、手数料だけは“据え置き”。
……誰のための制度か、少しずつ見えてきたやろ?
第4章|「ポイントだけ禁止で、手数料はそのまま」って、おかしない?
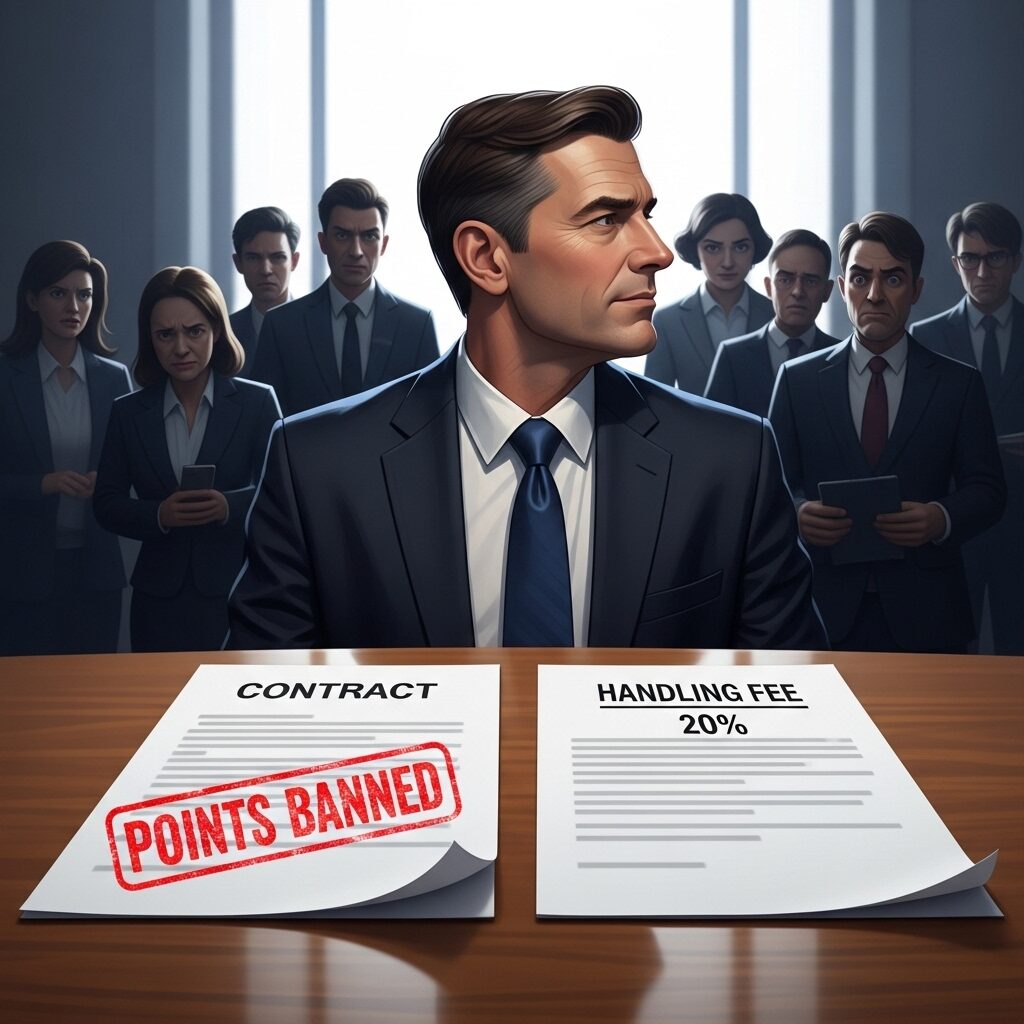
このポイント廃止を主導したのは、総務省や。 中でも旗振り役として名前が挙がっているのが、自治税務局 市町村税課 課長補佐・長谷川雄也氏。
彼は複数のメディアでこう語ってる。 「ポイントや返礼品目当ての“節税商法”は制度の趣旨に反する」と。
たしかに理屈としては、そうかもしれへん。 でもな── その裏で動いてた“高額手数料ビジネス”は、なぜ見逃されたままなん?
たとえば楽天ふるさと納税など、多くの仲介サイトでは、 自治体が寄附額の10〜20%もの手数料を支払っている。
■ 例:5万円の寄附 → 手数料 最大1万円(20%)
この手数料には、掲載・決済・発送代行などの業務費が含まれると言われとるけど、 自治体が競争的にサイトを選べず、言い値で払ってる実態もある。
さらに言えば、過去には“ポイントの原資”を自治体が負担してたケースもある。
(※公式には「全額企業負担」が原則やけど、実際はグレーな事例も)
そのうえで今回、「ポイントは禁止。でも手数料はそのまま」で通されたんや。
──これ、ほんまに「制度の健全化」って言えるんか?
名前出すのが過激やって言う人もおるかもしれん。 でもな、制度をここまで大きく変える判断をしたんやったら、 ちゃんと責任も名前も出るべきやと、僕は思う。
制度の“歪み”を残したまま、「改革」とだけ言うて終わらせる。 そんなやり方、納得できへんで。
第5章|この制度に“ゴーサイン”を出した政治家の責任は?
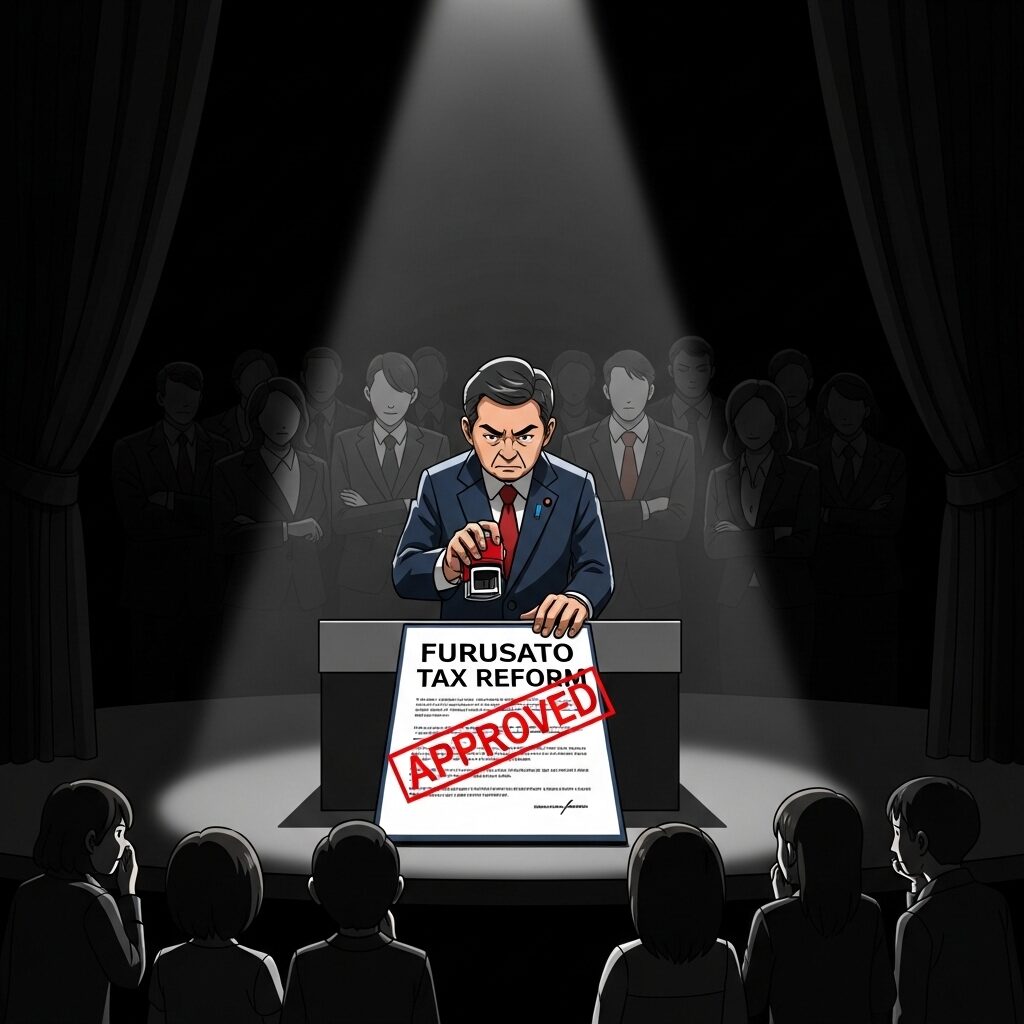
今回のルール改正を最終的に承認したのは、当時の総務大臣──松本剛明氏(自由民主党)や。
課長補佐クラスが旗を振るても、政治的に「通す」には大臣の決裁が必要なんや。 そして、その大臣は自民党。
……ほな、これは「官僚だけ」の責任なんか?
僕はそうは思わへん。
結局この法案、誰が得して、誰が損して、誰が責任取ってへんのか── そこまで含めて「構造」やと思うんよ。
「節税商法は制度の趣旨に反する」──たしかにそれは一理ある。 でも、金の流れを見直すんなら、まず“高額な手数料”のほうが先ちゃうんか?
国民の還元をゼロにして、企業の利益は据え置き。 それで「制度が良くなりました」って言われても……
誰が信じるねん、それ。
そして── この制度変更によって得をした企業と官僚。
損をした国民と自治体。
そういう“見えにくい力関係”に、ちゃんと光を当てて、 「誰が責任取るべきやったんか」を考える必要があると思うんや。
ほんで、政治家も「得をしとる」んや。
例えば……
- 改革アピールで“やってる感”を演出できる
- 都市部への税流出を抑えることで財務省との関係維持
- 仲介企業の利益を守ることで、将来的な政治献金や支援を得やすくなる
つまり、「制度の見直し」と言いながら、政治的にも“都合のいい改正”やった気がする。
少なくとも僕は、こんな静かな“収奪”を、 「ただの制度改正」やとは思わへん。
🔍 補足:官僚が「得した」とされる構造とは?
官僚は直接お金をもらったわけやない。 でも、制度設計やルール運用を通して、間接的なメリットを得たという指摘は多い。
① 天下り・利害関係企業との関係強化
- 仲介サイトを運営する企業に、官僚OBが“顧問”として就職している事例もある。
- 制度設計の段階で有利な仕組みをつくれば、将来的なポストを得る“布石”になる。
② 出世のための“改革実績づくり”
- 「節税商法を是正した」「制度を見直した」など、見た目の“改革”は人事評価でプラス。
- 実態がどうあれ、「やりました」と言える構造をつくることが目的化している。
③ 責任回避構造
- ポイント還元だけを「悪」として規制し、手数料や企業の利益はスルー。
- 「国民のため」と言いつつ、実際は企業も官僚も守られる構造になっとる。
──これが、「静かな収奪」の正体なんやと思う。
第6章|この制度は、誰のために存在しているのか?

ふるさと納税って、ほんまは「税金を使って、応援したい地域を支える」制度やったはずや。
せやのに今は── **「税金を企業経由で、間接的に回収される仕組み」**に近づいてきてしもてる。
言い方変えたら、 “還元がない分、実質的に負担が増えて、企業の取り分はそのまま”。
企業がすべて悪いとは言わへん。 でも、ポイントで集客していた企業だけが“悪者”にされて、 手数料ビジネスで儲けてたサイトは据え置きって、それはバランスおかしない?
🔍【補足】“すべての企業”が悪いわけやない
今回の制度変更で「企業が得をした」とは言っても、
すべてのふるさと納税サイトが同じ構造ではない。
たとえば──
| 種類 | 特徴 | 今回の影響 |
| 楽天ふるさと納税/au PAY ふるさと納税 | 寄付額の数%を“ポイント”としてユーザーに還元していた | → 還元禁止で大きな打撃。ユーザー離れも発生 |
| さとふる/ふるなび/ふるさとチョイスなど | ポイントはなし or 少なめ。主に“掲載手数料”や“システム利用料”で収益 | → 今回の影響は少なく、むしろ競合減少でプラスの可能性も |
ポイント集客で努力してた企業は、明確に“打撃”を受けてる。
一方、手数料で稼ぐ構造だった企業は、ほぼノーダメージや。
だからこそ問題なのは──
「ポイントだけを悪者にして、手数料ビジネスはそのまま」という“選別的な健全化”の姿勢やと思う。
国民の“応援したい気持ち”を利用して、 手数料だけが残っていく。
ほんで、気がついたら 「応援」やのうて「回収」になってる──そんな制度に変わってしもてるんや。
僕はこれを、「ただの制度改正」とは思わへん。
第7章|だから僕は、“声”を残しておく

僕はこの制度を否定したいんやない。 ふるさと納税って、ちゃんと使えばええ制度やと思う。
でもな、「誰も責任を取らずに、静かに国民だけが損する構造」が広がるのは見過ごせへん。
なんとなく、「しゃあないか」で済ませるんやなくて、 「これ、ほんまにええ改正やったんか?」って立ち止まって考えてほしいんや。
だれかがちゃんと声を上げな、 この国は「静かに税金を吸い上げられる社会」になってまう──いや、もうなってるんや。
たとえば、iDeCo(個人型確定拠出年金)もそうや。 「節税になるで」って言われて始めたら、引き出す時にはしっかり課税される。 しかも、以前は“5年”やった受け取り期間が、今は“10年”に伸びてたりする。 結果的に、国に長く預けさせられて、課税タイミングもコントロールされるんや。 退職金控除を使って“非課税で受け取れる枠”も、分割されることで目減りするケースもある。
政治家は選挙で落とせる。せやけど、官僚は名前すら知られんまま、制度をいじっても責任は問われへん。
ちゃんと政治家が見張ってなあかんやん。見張ってへんかったら、また選挙で落とすだけやで。
「静かに削られる構造」──これに気づいてない人が多すぎる。
「おかしいと思ったら、ちゃんと疑う」 それが、今の僕らにできる“小さな抵抗”やと思う。
”制度の裏にある“構造のゆがみ”に、静かに怒る人たちが増えることを願って。”
- ※本記事は筆者の見解・調査に基づく社会批評であり、全ての構造や意図を断定するものではありません。制度の経過や今後の動向について、最新の公式発表もご参照ください。
▶ 合わせて読みたい記事
『残された“3球”で、なにができる?──サンキューピッチと僕の人生』
小さな違和感に気づいたとき、僕らには何ができるんやろう。
『激しい雷雨の日に、僕が「守ること」を学んだ話』
災害も制度も、ほんまに怖いのは「気づきにくいリスク」やと思う。
『国民ファーストなんて嘘やん──略称「民主党」と書けば立憲行き? この国は誰のために選挙しとるんや。』
名前のマジックで票が流れるこの国の選挙──ほんまにええんか?



コメント